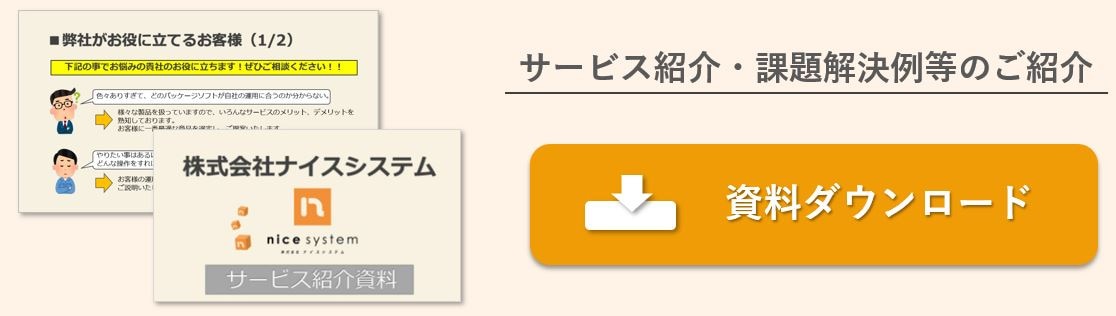【2025年4月施行】育児・介護休業法の改正ポイント
2024年5月に育児・介護休業法が改正され、2025年4月より順次施行となります。全企業が対象となり、育児休業・介護休業などに関する新たな義務が発生するため、対応のポイントを押さえる必要があります。 本記事では、2025年4月からの改定概要、ポイントや注意事項、手続きの手順を解説します。
記事を見る2024年5月に育児・介護休業法が改正され、2025年4月より順次施行となります。全企業が対象となり、育児休業・介護休業などに関する新たな義務が発生するため、対応のポイントを押さえる必要があります。 本記事では、2025年4月からの改定概要、ポイントや注意事項、手続きの手順を解説します。
記事を見る働き方改革が進む今、休暇制度も進化しています。企業は多様な働き方に対応するため、特別休暇の種類を拡充しています。 本記事では、労務担当者が知っておくべき法定休暇(年次有給休暇など)と法定外休暇(慶弔休暇など)の種類、有給休暇・無給休暇・欠勤の違いを分かりやすく解説します。会社に勤め始めたら知っておきたい、休暇の基礎知識をわかりやすくまとめました。
記事を見る随時改定(月額変更届)とは、収入が大きく変わったときに社会保険料の計算基準となる「標準報酬月額」をその変動に合わせて見直すための処理のことです。昇給・降給、ボーナス増減など、収入に変化があった場合は、この手続きが必要となる場合があります。 本記事では、随時改定(月額変更届)の要件やや注意事項、手続きの手順を解説します。
記事を見る賞与とは、会社が毎月の給与とは別に従業員に対して支払う一時金のことです。賞与計算は通常の給与計算に比べて計算方法が複雑です。そのため、人的ミスや非効率な作業に悩みを抱えている人事労務担当、経理担当も多いのではないでしょうか。 本記事では、賞与で控除される社会保険料の計算方法について具体例を紹介しながら解説します。給与の社会保険料とは計算方法が異なるため、正しく理解しておくことが重要です。
記事を見る「弥生会計」や「やよいの青色申告」で有名な弥生株式会社が販売している会計ソフトの弥生シリーズですが、2024年秋提供予定の弥生25シリーズからデータコンバートが2世代間に限定される案内が弥生ホームページに掲載されています。 本記事では、この変更に伴う対応について解説していきます。
記事を見る2024年の郵便料金値上げは、企業や個人に様々な影響を及ぼすことが予想されます。特に、郵送業務の多い企業は、これによるコスト増加に直面する可能性があります。 本記事では、郵便料金の値上げによる企業への影響や郵送コストを抑える方法、請求書を電子化するメリットなどを解説します。請求書業務の効率化やコスト削減を検討している場合は、ぜひご参考ください。
記事を見る賃上げ促進税制は、賃上げや人材育成に投資した費用が前年度より一定以上増加していると、所定の税額控除が受けられる制度です。 近年、政府は「賃上げ」を強く推進しており、中小企業にとっても人材確保や従業員のモチベーション向上など、賃上げは多くのメリットをもたらします。しかし、人件費増加という課題も伴います。本記事では、中小企業向けの「賃上げ促進税制」の仕組みと注意点について、わかりやすく解説します。
記事を見る算定基礎届は、健康保険や厚生年金保険、介護保険の保険料を計算するための報酬月額を決定するために、事業主が毎年7月頃に日本年金機構へ提出する書類です。対象となる事業所は、必ず算定基礎届を提出しなければなりません。 算定基礎届は、社会保険料の計算に必要な標準報酬月額を決定するうえで重要な意味を持ちます。本記事では、算定基礎届を提出する目的や書き方ついて紹介します。
記事を見る近年、企業では複数のシステムを使いこなすことが当たり前となっており、システム間のデータ連携が大きな課題となっています。API連携は、この課題を解決するための有効な手段として注目されています。 今回はそのAPI連携についての簡単なご紹介と、このAPI連携を活用することでどのように業務の効率化やコスト削減することが出来るか解説していきます。
記事を見る近年、企業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されています。様々な企業で業務効率や労働環境を改善するためにDXの取り組みが求められています。一方で、DXをうまく進められない企業や、DXによる成果を実感できていない企業が多いのも事実です。 本記事は、「バックオフィスのDX化が進まない理由・失敗例から成功ポイントを解説ー前編-」の後編です。ぜひ最後までご覧ください。
記事を見る当社では、メーカー認定のインストラクターが、30社以上の業務ソフトを取扱い、導入をサポート致します。マルチベンダーとして中四国(四国四県・広島・岡山)を中心に活動させていただき、それ以外のエリアではオンラインでもご対応致します。
ご興味のある方はぜひ、無料でダウンロードできる資料をご覧ください。